
朝9時30分頃。
タクシー7台に分乗し、到着。
何はともあれ、集合写真。
木村運送様にて |

|

朝10時。
各講中、ご挨拶。「おはようございます!」
ここから始まります。 |
 |

警固提灯を先頭に各町内会所にご挨拶行列スタートです。。 |
 |
 |
 |
 |

まずは番場の本会所から。 |

そして番場青年会所。
|
 |

西に進み、片町へ。 |

東に神戸会所。 |

ここで一旦、大鳥居をくぐり
大國魂神社へ参拝。 |
 |

皆さん、お財布の準備ですかね。
参拝後、参道を南へ。西馬場に向かいます。 |

列は一旦西馬場で解散し、
最初の講中詰所に戻ります。
ここで御馳走になって、いよいよ御太皷の準備が始まります。
|

張替えを終えたばかりの御太皷。
国産欅では国内最大のくり抜き胴の御太皷。
ロップが掛かっていない時の姿、好きなんですよね〜。
ずっと見ていても飽きません。(笑)

講中のロップ掛けが始まりました。
昭和27年5月5日におろされた御太鼓。
当時の各講中の名士の御名前が刻まれています。
混乱を避けるため、各講中から数名ずつがロップ掛けを担当し分担します。
なので、そうでない人はというと、、

こんな感じ。 とか、、、、、

こんな感じで、じっと待ちます。
「できたの〜?まだなの〜?」
 |

講中引き渡し式。
ここから鈴木太皷長を筆頭に
講中の責任で神事に臨みます。
各団体役員様が叩き初めをします。
|

さあ、出発です。
朝と同様、西に向かいます。 |

屋敷分の先まで進んでUターン。。 |

途中、水分補給しながらですね。
今日は暑い。 |

そして、列は片町まで戻ってきました。 |
 |
 |

片町会所前。
|
 |
 |

こちら片町は、今でもお祭りの前には先輩たちが集まって、
御太皷の練習をするんだそうです。練習必要ないのにね。(笑)
お手本になる先輩たちがたくさんいらっしゃいます。 |

この方にも、あこがれた叩き手は多いですね。
素敵です。 |

無心で。一生懸命。叩く。
とにかく太皷が大好き。 |

みなさんお上手です。 |

一言でいうとタフな先輩。
安定してます。 |

ここは叩き手が多いので、講中は警固に専念。(笑)」 |

なおも列は進みます。 |
 |

番場も過ぎて、 |

御旅所を越えます。
|

引き綱は、めいっぱい広げて
ど真ん中を進みます。 |

ここ、いいですね〜。
|

一番気持ちいい。
|

神戸で会所側に太皷を返して、表向きにします。
|

見守る次世代。たくましい。
しばし叩く。
|

大鳥居前までこのまま進みます。 |

欅並木を南に折れると
Jcomのテントが。 |

西馬場に向かいます。
|
 |

上乗りは四人ね。四人。 |

上乗り警固四人のまま、大鳥居に向かいます。
|
 |

ささらの道浄めを先頭に、
いよいよ御太皷送り込みです。 |
 |

準備はOKですね。 |

大鳥居をくぐり、参道を進みます。 |
 |

後ろの観客に気を付けながらも
御太皷は叩き続けます。 |

隋神門です。 |
 |
 |

中に入ります。
|

何度か切り返し、
定位置へ。 |

上乗り、四人ね。(笑) |
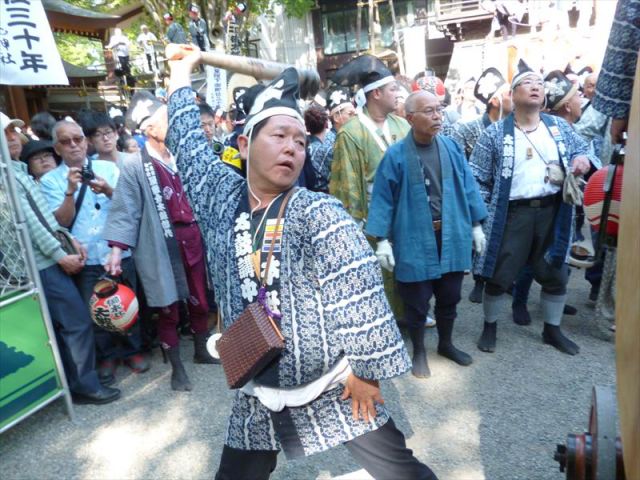
O氏。 |

ミニ総代。 |

シゲさん。 |
 |
 |

調布の同級生。(笑) |

仲間の御子息。次世代ですね。 |

きみちゃん。 |

三鷹の牟礼(二之宮)の大先輩。
上手ですね〜。
|

五六之宮愛皷会ね。 |

これにて一旦打ち止め。
6時の号砲まで、しばし静寂のひと時となります。

なわけで、いったん上鈴木はお食事に。

|

こちらのお店ですね。
人生と書いて「ひといき」というお店です。
店内広々で、お料理もおいしかったです。 |